
先日の伝統芸能選考会で踊った雑踊の演目「花風」。私が琉球舞踊を始める前から憧れていた踊りである。
しかし選考会の稽古では、常に師匠から貶されていた。「素人じみた踊りをするな」、前日までも「色気が無い」と、自分でもどうにもならない評価だった。
そして当日、それまでとは真逆の反応の師匠。「今日の花風には納得した」と一言。なんの期待もなかったため、その言葉も褒め言葉ではなく、今日の演技に対する評価と私は受け止めた。
演技とは、一日一日違って、変わるものだ。
だから糠喜びほど自分を貶めるものはない。
厳しく言われているうちが、それに対する忍耐と成長の時期であるが、一旦認められると同時に芸は下手になりやすくもなる。
プロフェッションとは心の問題であると感じる。他人からの評価、社会からの評価、それもあるだろうけれど、それ以上に、自分の芸を自分自身で磨き上げていくための精神性なのだ。
選考会での栄えある結果は、完成形ではなく、寧ろ踊り手としてのスタートラインである。だからこそ、ここから自分を厳しく見つめこの舞踊を研究していかなくてはならない。
今回は、私にとってもひとつの節目となった雑踊の演目の一つ「花風」について振り返ってみたい。
雑踊の由来
雑踊とは、琉球国が終焉を迎え、明治期以降に生まれた踊りのことをいう。
沖縄の古典舞踊は、御冠船の歓待など、琉球王朝の外交行事を中心に発展してきた。この舞が庶民の暮らしにまで広がり、親しまれるようになったのは、廃藩置県を経たあとの沖縄からだ。
そうした時代のなかで、庶民の風俗を映した踊りが生まれた。それが、雑踊なのである。
「花風」は代表的な雑踊の演目の一つである。
この曲の主題は、辻の遊女が、愛しい人を見送ろうと、人目を憚り港のそばの三重城に立つ場面にある。
しかし、船の足はあまりにも速く、一目しかその姿を捉えられなかった——その切なさを歌っている。

歌意
中踊では「花風節」、入羽では「下出し述懐節」で構成されている。
三重城に登て 手巾持ち上げれば
(みぐすぃくにぬぶてぃ てぃさじむちゃぎりば)
早船の慣らひや 一目ど見ゆる
(はやふにぬなれや ちゅみどぅみゆる)
〈花風節〉
朝夕さもお側 拝み馴れ染めて
(あさゆさんうすば をぅがみなりすみてぃ)
里や旅しめて 如何す待ちゆが
(さとぅやたびしみてぃ いちゃすぃまちゅが)
〈下出し述懐節〉
花風節ではまさに見送る遊女の情景が表現されている。
一方、下出し述懐節の歌意は、
”朝夕いつも側にいて、慣れ親しんだ貴方は旅立ち、私は一人でどうお待ちしたらいいのでしょうか”
愛する人が旅立ち、独り侘しい胸の内が表現されている。
見送る情景、胸の内の想いとが、しっとりと合わさり寂しくて切ない。この踊りの美しさである。
歴史
『花風』は明治二十八年頃にできたとされている。
辻の端道(現在の那覇市辻町あたり)に本演芸場があり、そこで生まれたとされている。その当時、「各劇場は、古典ものに飽きた観客を引き付けるために、争って創作に力を注いだ」1) とされており、雑踊が民謡中心であったのに対して、『花風』は身なりは現代でありながら、曲に古典を用いられたことで、新鮮なものとして人々の目に映ったとされる。
装束
紺地の絣をウシンチーに着付け、白足袋を履く。手には花染手巾。肩に掛けたり、手に持つなどして踊る。
頭は、辻結に銀のジーファーを挿す。
質素さに、遊女の洒落感が漂う装い。また絣の着物も、「七かせ」という柄を着る。浜千鳥で着られている絣と柄が異なり、細かい模様で織られていることも小洒落た雰囲気を助長させる。

来る芸能祭でも「花風」を舞う予定である。
この踊りを生涯、大切に踊っていきたい。
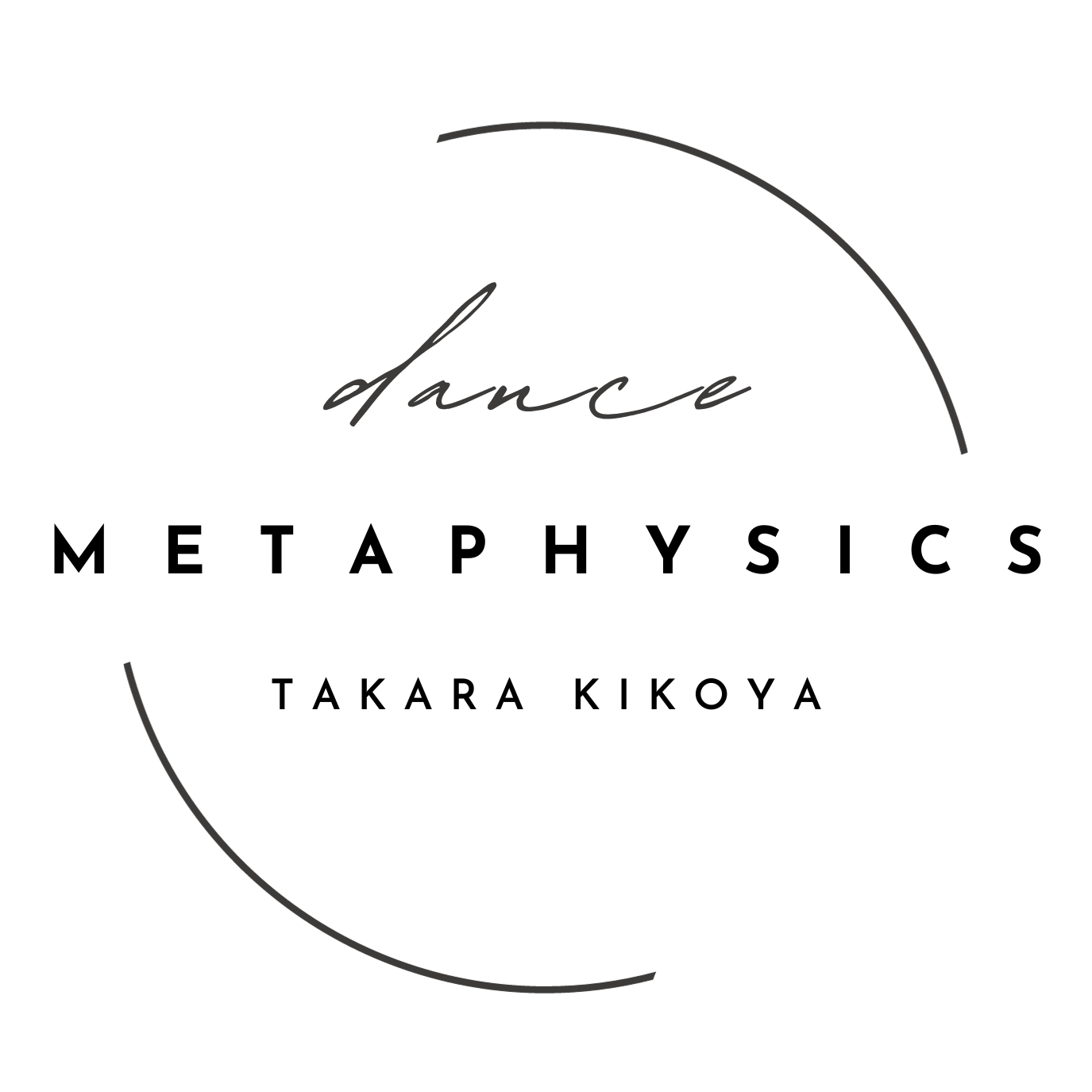


コメント